前回に引き続き金融庁にあった投資についてのページで勉強したいと思います。https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/knowledge/basic/index.html
今回は分散投資です。
分散投資
リスクを減らす方法の一つに分散投資があります。分散投資には、「資産・銘柄」の分散や「地域の分散」などのほか、投資する時間(時期)をずらす「時間(時期)分散」という考え方があります。
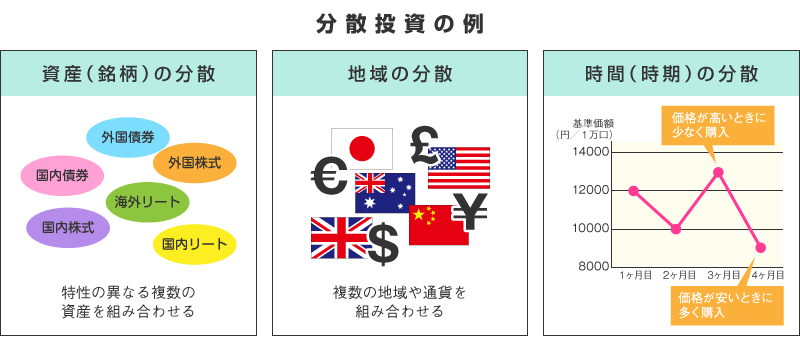
資産・銘柄の分散
投資対象となる資産や、株式等の銘柄には様々なものがありますが、それぞれの資産・銘柄は、常に同じ値動きをするわけではありません。例えば、一般的に、株式と債券とでは、経済の動向等に応じて異なる値動きをすることが多い(例えば株式が値上がりするときには債券が値下がりする等)と言われています。
こうした資産や銘柄の間での値動きの違いに着目して、異なる値動きをする資産や銘柄を組み合わせて投資を行うのが「資産・銘柄の分散」の手法です。こうした手法を取り入れることで、例えば特定の資産や銘柄が値下がりした場合には、他の資産や銘柄の値上がりでカバーする、といったように、保有している資産・銘柄の間で生じる価格変動のリスク等を軽減することができます。
なお、投資信託の中には、投資信託の運用者(ファンドマネージャー)が、様々な資産や地域を対象に投資を行う「バランス型」のものもあります。投資信託は、ファンドマネージャーにお金を預けて、その運用を任せる仕組みですので、こうした種類の投資信託を購入すると、様々な種類の資産を選択して自分で投資を行わなくても、購入した投資信託のファンドマネージャーを通じて、「資産・銘柄」や「地域」を分散させることが可能です。
地域の分散
投資対象の資産や株式等の銘柄に様々なものがあるのと同様に、投資する対象が存在する地域も日本には限られません。したがって、投資対象の資産や銘柄の価格は、投資の対象となっているものが存在している国や地域の状況、為替変動などによって、様々な値動きをすることになります。
そこで、こうした投資対象地域の性質による値動きの違いに着目して、異なる状況にある地域の資産や銘柄、通貨を組み合わせて投資を行うのが「地域の分散」の手法です。国内と国外、あるいは先進国と新興国のように、異なる国・地域の資産・通貨を組み合わせて投資を行うことで、例えばある地域の経済状況の変化等によって、保有している特定の資産・銘柄が値下がりした場合には、他の資産や銘柄の値上がりでカバーする、といったように、保有している資産・銘柄の間で生じる価格変動のリスク等を軽減することができます。
時間(時期)の分散
「資産・銘柄の分散」や「地域の分散」で見てきたとおり、個々の資産や銘柄はその性質に応じて様々な値動きをします。そこで、一度に多額の投資を行うのではなく、積立投資信託のように、少額・定期定額で投資を行うことで、時期による値動きに応じて、価格が高い時期には少なく、価格が低い時期には多く投資を行うのが「時間(時期)の分散」(ドル・コスト平均法)の手法です。
「時間(時期)の分散」の手法を採用すると、経済の動向等によって、高い価格で投資を行う時期と低い価格で投資を行う時期が生じることになりますが、長い目で見ると、一回あたりの投資価格は平準化されていきますので、短期的な急な値下がりなどが生じても、それによって生じる損失の程度を軽減することが可能になります。
(「資産(銘柄)の分散」・「地域の分散」の例)
日本だけではなく、様々な国や地域の株式等(証券)に投資することを考えてみましょう。「異なる地域」の「異なる種類」の架空の証券を想定して、いずれの証券についても、最初は10,000円で購入し、その後、以下のグラフのような値動きをしたものと仮定します。
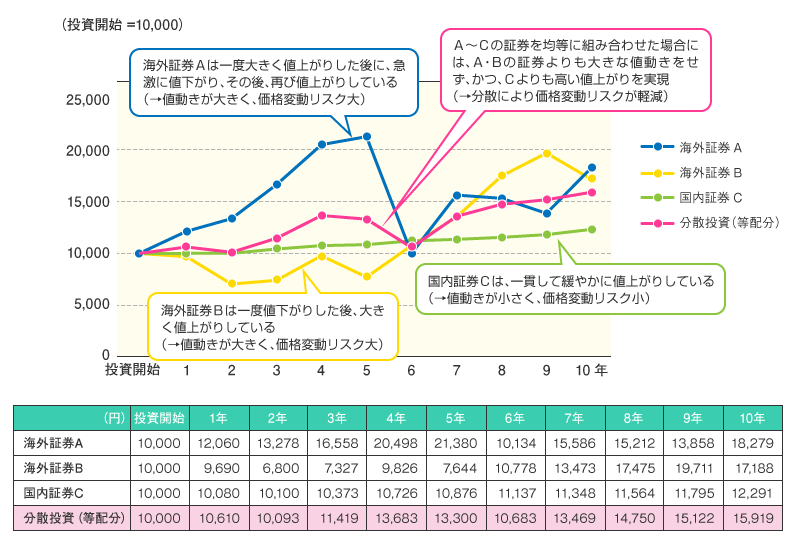
購入した証券は、それぞれ異なる値動きをしています。例えば「海外証券A」は、5年目まで大きな値上がりが続いた後に急激に値下がり、その後、持ち直しています。また、「海外証券B」は、最初に値下がりをしましたが、その後に大きく値上がりしています。他方で、「国内証券C」は、一貫して緩やかな値上がりを続けています。
次に、「分散投資(等配分)」の場合の動き(上記のA~Cまでの証券をそれぞれ同じ配分で持っていた場合の平均の値動きを示しています。)を見てみましょう。
上記のとおり、特に「海外証券A」や「海外証券B」の価格は年によって大きく変動していますが、これら2つと「国内証券C」を組み合わせた平均である「分散投資(等配分)」の値動きは、比較的安定した値動きを見せています。これは、対照的な値動きをした「海外証券A」と「海外証券B」、そしてなだらかな上昇を続けた「国内証券C」のそれぞれの値動きが合わさったことで、異なる種類の証券での運用という意味での「資産(銘柄)分散」と、国内外の証券での運用という意味での「地域の分散」が作用し、全体として安定的な値動きが実現できたことを示しています。
では、10年目にはそれぞれの投資成果はどのようなものであったのでしょうか。
これまで見てきたとおり、海外証券A・海外証券Bは、大きな値動きを続けており、価格変動のリスクが大きく、長期に保有するには大変だったかもしれません。一方で、国内証券Cは、安定的に上昇しました。しかし国内証券Cは10年目でようやく1万2千円台となり、ほかの資産よりも物足りないかもしれません。これらを併せ持った分散投資(等配分)の成果をみると、大きく上昇はしませんでしたが、元本の1万円を割り込むこともありませんでした。価格変動リスクの大きい海外証券A・Bほどの収益はありませんでしたが、国内証券Cよりも利益を生みました。10年間の長期投資で長く持ち続けるためにも、安定性と収益性は重要です。
(「時間(時期)の分散」(ドル・コスト平均法)の例)
次に、毎月1万円ずつ、1年間の間、ある投資信託を購入し続ける場合を考えてみましょう。購入する投資信託は、以下のグラフのような値動きをしたものとします。
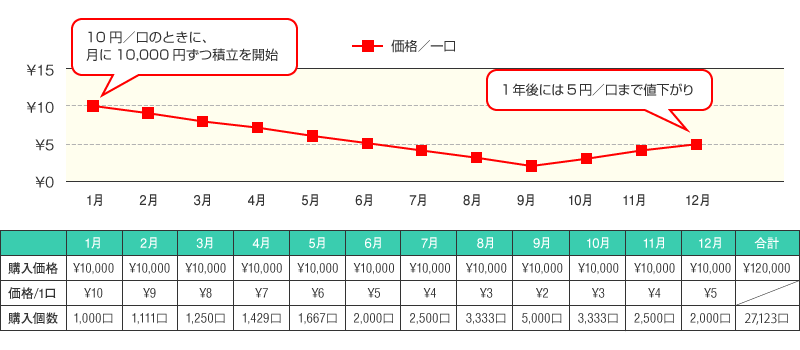
最初に投資信託を購入した1月時点の単価が1口10円だった場合、10,000円で1,000口購入できることになります。他方で、最も値が下がって1口2円になった9月時点では、同じ1万円で5,000口購入できることになります。
1年間経った時点での投資総額は、1万円/月×12ヶ月ですので、120,000円、購入した投資信託の総口数は27,123口になっています。
- ○12月末時点の投資信託の価額:5円/口×27,123口(総投資口数)=135,615円
- ○12月末時点の投資総額:10,000円/月×12ヶ月=120,000円
- ○損益:135,615円-120,000円=15,615円(利益)
仮に12月の時点で投資を止めた場合、12月時点での1口当たりの価額は5円ですので、この時点で保有している投資信託の価額は、5円/口×27,123口で135,615円になり、投資総額の120,000円と比較すると、15,615円(135,615円-120,000円)の利益が出ていることが分かります。
上のグラフを見ると、最初に投資信託を購入し始めたときよりも、投資を止めたときの方が、1口当たりの価額は下がっていますが、計算してみると、結果的には利益が出ていたということになります。これは、投資の時間(時期)を分散したことで、1口当たりの投資価額が平準化され、高い値段の時に投資した分の値下がりが、低い値段のときに投資した分の値上がり分でカバーされた結果ということができます。



コメント