11月3日は「文化の日」です。ウイキペディアには以下の通り文化の日について説明がされています。
文化の日は、日本の国民の祝日の一つである。日付は11月3日。1946年11月3日の日本国憲法公布を記念して制定された。
概要
歴史
文化の日は、国民の祝日に関する法律(祝日法、昭和23年7月20日法律第178号)第2条によれば、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨としている。
1946年(昭和21年)に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法で「文化の日」と定められた。日本国憲法は、公布から半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されたため、5月3日も憲法記念日として国民の祝日となっている。
休日としては、1873年(明治6年)に公布された年中祭日祝日の休暇日を定む(明治6年太政官布告第344号)以降1911年(明治44年)までは天長節、1927年(昭和2年)に改正された休日に関する件(昭和2年3月4日勅令第25号)以降1947年(昭和22年)までは明治節として、明治天皇の誕生日による祝日となっている。
祝日法制定当時、参議院文化委員長として祝日法制定の際中心的役割を担った山本勇造が政界引退後に書いた当時の回顧録「文化の日ができるまで」には明治節に関する記述は一切ない。山本によれば、元々、憲法発布は11月1日の予定であったが、施行日がメーデーと重なるという理由で直前に11月3日に変更されたのだという。山本ら参議院側は11月3日を憲法記念日とすることを強硬に主張したが、GHQ側が、11月3日だけは絶対にだめだと主張し、衆議院が5月3日を憲法記念日とすることに同意してしまい、参議院側が孤立する事態になった。そのとき突然GHQ側から、憲法記念日という名でない記念日とするなら何という名がいいか、という話を持ち出してきたという。
1948年(昭和23年)6月18日の参議院文化委員会において、山本勇三は「憲法において、如何なる國もまだやつたことのない戰爭放棄ということを宣言した重大な日でありまして、日本としては、この日は忘れ難い日なので、是非ともこの日は残したい。そうして戰爭放棄をしたということは、全く軍國主義でなくなり、又本当に平和を愛する建前から、あの宣言をしておるのでありますから、この日をそういう意味で、『自由と平和を愛し、文化をすすめる。』、そういう『文化の日』ということに我々は決めたわけなのです」と説明している[2]。
また、同年7月4日の参議院本会議においては「十一月の三日を文化の日といたしましたのは、これは明治天皇がお生まれになつた日であり、明治節の祝われた日でございますが、立法の精神から申しますと、この日は御承知のように、新憲法が公布された日でございます。そうしてこの新憲法において、世界の如何なる國も、未だ曾て言われなかつたところの戰争放棄という重大な宣言をいたしております。これは日本國民にとつて忘れ難い日でありますと共に、國際的にも文化的意義を持つ重要な日でございます。そこで平和を図り、文化を進める意味で、この日を文化の日と名ずけたのでございます。平和の日といたしましてもよいのでありますが、それは別に講和締結の日を予定しておるのでございますので、それを避けたのでございます」と説明しており、明治節だからではなく、新憲法、特に戦争放棄を謳った第9条が公布された日であるから祝日としたという説明がなされている[1]。
また、憲法公布日が11月3日になったことについては、入江俊郎によれば、施行の候補日として挙がっていた5月1日、5月3日、5月5日のうち、5月1日はメーデーであるためふさわしくないと判断され、5月5日は端午の節句であり、男の子の祭りであるから男女平等の憲法にふさわしくないこと、また武の祭りであるから戦争放棄の憲法にふさわしくないと判断されたため、消去法で5月3日に公布することになり、その半年前である11月3日に公布することが決まったとされており、明治節に合わせて公布日を決めたのではないということである。
行事
- 皇居で文化勲章の親授式が行われる。
- 海上自衛隊で、基地・一般港湾等に停泊している自衛艦において、満艦飾が行われる。
- 文化の日を中心に、文化庁主催による芸術祭が開催される。
- 博物館や美術館の中には、入館料を無料にしたり、様々な催し物を開催する所もある。
- 日本武道館で全日本剣道選手権大会が開催され、NHK総合テレビジョンで生放送される。
また、この日は晴天になる確率が高い「晴れの特異日」とされる。
戦前の昭和前期には「明治節」明治天皇の誕生日として祝日だったらしいです。明治天皇の遺徳をしのび、明治時代を追慕する目的で制定した。
国民の祝日は政治的な意図によりつくられていることを知る。特に「文化の日」はその色が濃い。「明治節」明治天皇の功績をたたえる国民の祝日とされた。国民に天皇家のお陰で祝日とされていることを印象付けることとなる。天皇と国民の関係性とその位置づけを明確にする意図が感じられる。また、11月3日は戦後には「文化の日」に変わる。終戦直後日本はGHQにより統治される。GHQは天皇家と国民の分断を図ろうとする。天皇は神ではない。人間なのだということを強くすり込もうとする。日本全国を巡幸もGHQの意図があったと思う。終戦前には国民(平民)は天皇と目を合わせることはいけないこととされていた。しかし、戦後の巡幸で天皇は国民と同じ人間であり、神ではない事を知ら締めさせることとなった。天皇家と国民を分断するためには天皇家由来の祝日は在ってはならない存在。そのため「明治節」は廃止となった。また、比較的新しい祝日である「海の日」や「山の日」がつくられたこと。特定の月日を固定しないで○月の第2月曜が祝日とかに変えて3連休となるように変更したことは政治家の人気取りの施策としか思えない。祝日はうれしいが、その決められた経緯などを思うと複雑な気持ちとなる。

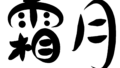

コメント